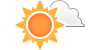KANSAIウオーク2021 奈良・斑鳩町エリア
-
今日 4/29(火)
-
4/30(水)
23 10
-
5/1(木)
25 13
-
5/2(金)
22 15
-
5/3(土)
26 13
-
5/4(日)
24 14
-
5/5(月)
24 11
-
アプリでコースを検索する(アプリDL画面へ)
-

-

コース詳細
-
-
- ② 龍田の街並み
- 龍田の街並み→「龍田」は古く『万葉集』にも登場する地名。『万葉集』に記される「龍田越え」は、大和と河内を結ぶ道で、法隆寺の南から龍田大社(本宮)の前を通り、大和川北岸の龍田山を越えて河内へと抜ける道である。平城京遷都後は竹内街道に代わって、平城京と難波(なにわ)を結ぶ最も主要な幹道となった。中世に入っても交通の要衛で、龍田市が開かれて賑わい、大坂冬の陣・夏の陣の際には、徳川方の大軍がこの道を通って大坂城へと向かった。現在も、街道沿いに伝統的な街並みが残る。写真は旧街道の西側入口にある明治2年(1869)創業の太田酒造の外観。地酒と奈良漬けで有名。
-
- ③ 龍田神社
- 龍田神社→聖徳太子(厩戸皇子:うまやとのみこ)が法隆寺の建設地を探し求めていた時に、白髪の老人に化身した龍田大明神に出会い、「斑鳩の里こそが仏法興隆の地である。私はその守護神となろう」と告げられたので、斑鳩の地に法隆寺を建立し、法隆寺の鎮守として龍田大明神を祀ったと伝える。元来の龍田大社(三郷町立野)を「本宮」と呼ぶのに対し、こちらの龍田神社は「新宮」と呼ばれる。能楽の大和四座の内の一つ「金剛流」は当地発祥の坂戸座を源流とすることから、境内に「金剛流発祥之地」の石碑が建てられている。
-
- ④ 藤ノ木古墳
- 法隆寺の西方約350mに位置する直径50m以上の円墳。6世紀後半の築造と考えられる。これまでの発掘調査の結果、横穴式石室には未盗掘の家形石棺が安置され、2人の人物が葬られていたほか、金銅製の冠や履など豪華な副葬品が埋葬当時のまま発見された。また、石棺と奥壁の間からは華麗な装飾が施された金銅製の馬具が出土した。これらの出土品は国宝に指定され、藤ノ木古墳自体も国の史跡に指定されている。法隆寺に残る記録には、「ミササキ」「ミササキ山」とあおり、崇峻天皇(すしゅんてんのう)陵と伝えられてきた。
-
- ⑤ 法隆寺⦅世界文化遺産⦆(有料)
- 斑鳩(いかるが)の地に法隆寺が建築されたのは推古天皇15年(607)のことで、亡くなった用明天皇(聖徳太子の父)の遺志を継いで、推古天皇と聖徳太子が薬師像を祀る斑鳩寺(法隆寺)を建てたことが始まりとされる。しかし最初の法隆寺は、創建から64年後の天智天皇9年(670)に火災で全焼したと日本書紀には記されており、それは現在「若草伽藍」と呼ばれている場所に建てられていた「四天王寺式伽藍配置」の寺であったと考えられている。現在の法隆寺はその後天武天皇の時代に再建に着工し、数十年の年月をかけて完成させたものと考えられている。法隆寺は金堂・五重塔を中心とする西院伽藍と夢殿を中心とする東院伽藍の二つの寺域で構成され、西院伽藍は中門を入ると右に金堂、左に五重塔が建つ様式で、「法隆寺式伽藍配置」と呼ばれる。敷地面積18万7千平方メートルにも及ぶ広大な境内には、19棟の国宝建築物をはじめ、国宝・重要文化財に指定された仏像など約190件が所蔵され、点数にするとおよそ3000点に達する。世界最古の木造建築が建ち並ぶ境内は、平成5年(1993)12月ユネスコ世界文化遺産に登録された。拝観料 一般1,500円/小学生750円
-
- ⑥ 中宮寺(有料)
- 創建当初は現在の場所から東へ500mほどの場所で、現在は中宮寺跡として整備され、残っている。聖徳太子が母の穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后の宮殿の跡を母の菩提を弔うために寺としたと伝えられる。太子が建立の宮の中間にあたることから、また、皇后のお住まいであったから「中宮寺」と呼ばれている説もある。天文年中(1532~55)に伏見宮貞敦親王の王女である尊智女王が入寺して以来、門跡(もんぜき)寺院となり、歴代皇女・王女が入寺した・円照寺・法華寺とともに大和三門跡に数えられる。本堂には国宝の木造 菩薩半跏像が安置される。寺伝では如意輪観音とするが、元来は弥勒菩薩として造立されたと考えられる。また国宝の天寿国繍帳(てんじゅこくしゅうちょう)は聖徳太子の死を悼んで、妃の橘大郎女(たちばなのおおいらつめ)が太子の往生した天寿国の様子を刺繍させたものと伝えられる。拝観料 大人600円/中学生450円/小学生300円
-
- ⑦ 斑鳩神社
- 法隆寺の北東に位置し、平安時代の天慶年間(938~947年)に法隆寺別当の湛照僧都(たんしょうそうず)が、自身が菅原氏の子孫であることから菅原道真を祀ったとのが始まりと伝えられる。当初は法隆寺が祭祀や管理を行っていたが、明治の神仏分離令で法隆寺村の管理となり、法隆寺の境内にあった白山社なども合祀された。以来、現在に至るまで、旧法隆寺村の産土神として信仰されている。秋祭りでは、10月9日の宵宮に法隆寺境内の御旅所まで神輿が渡御し、翌10日の本宮では神輿の前で僧侶の読経が行われた後、神輿が神社へ還御する。
-
- ⑧ 仏塚古墳
- 法隆寺の北に広がる丘陵、通称「寺山」から延びた尾根の先端部に立地する、1辺約23m方墳。6世紀末に築造されたと推定測される。埋葬施設は横穴式石室で、石室内からは馬具や土器などの他、鎌倉時代から室町時代にかけての仏像など、仏教に関係した遺物が出土している。「仏塚」という名称は、石室が中世に仏堂として利用されたことに由来すると考えられている。※仏塚古墳石室入口はご覧になれません。
-
- ⑨ 中宮寺宮墓地
- 天文年間(1532~1555)の伏見宮貞敦親王王女・尊智女王(そんちじょうおう)以来、中宮寺に入った歴代皇女・王女の墓所で、宮内庁が管理する。尊智女王、伏見宮邦房親王王女・尊覚女王、後西天皇皇女・髙栄女王、有栖川宮職仁親王王女・栄恕女王、有栖川宮職仁親王王女・栄暉女王、伏見宮貞敬親王王女・成淳女王の6つの墓と、後西天皇の供養塔がある。
-
- ⑩ 法輪寺(有料)
- 斑鳩町の三井にある法輪寺はその地名をとって「三井寺」とも呼ばれる。創建については、二つの説がある。一つは推古天皇30年(622)に聖徳太子が自らの病気平癒を祈願して建立を発願、太子の子である山背大兄王と孫の由義王が建立したというもので、もう一つは天智9年(670)の斑鳩寺炎上後に百済の開法師・円明法師・下氷新物が合力して建立したという説である。法隆寺、法起寺とともに斑鳩三塔と呼ばれた法輪寺の三重塔は、国宝に指定されていたが、昭和19年(1944)に落雷で焼失。現在の塔は作家の幸田文氏らが資金集めに尽力し、昭和50年(1975)に「最後の宮大工」と謳われた西岡常一氏の手によって再建されたものである。発掘調査の結果、創建当初の法輪寺は、法隆寺西院伽藍と同じ伽藍配置で、約3分の2の規模であることが明らかになった。講堂(収蔵庫)には、飛鳥時代に造られた薬師寺如来像・虚空蔵菩薩像の他、平安時代の十一面観音菩薩像・弥勒菩薩像・吉祥天女像・地蔵菩薩像など、国の重要文化財に指定された多くの仏像が安置されている。大人500円/中学生~高校生400円/小学生200円
-
- ⑪ 富郷陵墓参考地(伝 山背大兄王墓所)
- 地元で「岡の原」と呼ばれる丘陵の頂上部にある円墳で、聖徳太子の長子である山背大兄王(やましろのおおえのおう)の墓と伝承され、宮内庁が管理する。古墳時代中期の築造と考えられ、墳丘からは埴輪片などが出土している。推古天皇の没後、山背大兄王は、皇位継承をめぐって、蘇我蝦夷(そがのえみし)の推す田村皇子と対立し、結局、田村皇子が即位して舒明天皇となる。その舒明天皇の没後、中継ぎとして、舒明天皇の皇后が即位し、皇極天皇となったものの、その後継者をめぐって、山背大兄王は、古人大兄皇子の擁立を目論む蘇我入鹿(そがのいるか)と対立する。入鹿の攻撃を受けた山背大兄王は、皇極2年(643)11月に「斑鳩宮」(法隆寺東院伽藍周辺)で一族とともに自害を遂げ、ここに聖徳太子以来の「上宮王家」は滅亡した。
-
- ⑫ 法起寺⦅世界文化遺産⦆(有料)
- 推古天皇14年(606)に聖徳太子が法華経を講説した岡本宮の故地。推古天皇30年(622)、聖徳太子が死に臨み、長子の山背大兄王に宮殿を改め寺とするよう遺言したと伝えられる。岡本尼寺・岡本寺・池後尼寺・池後寺とも呼ばれ、四天王寺、法隆寺、中宮寺などとともに太子御建立七力寺の一つ。元来の伽藍配置は中門を入ると右に三重塔、左に金堂が建ち、法隆寺西院伽藍とは左右が逆で、「法起寺式伽藍配置」と呼ばれる。創建当初から残る建物は三重塔のみ。飛鳥様式の三重塔は、三重塔としてはわが国最古で最大である。収蔵庫内に安置される平安時代十一面観音菩薩像は本来、講堂の本尊で、重要文化財の指定を受ける。法起寺境内は国の史跡に指定され、ユネスコの世界文化遺産にも登録されている。拝観料 一般300円/小学生200円
-
- ⑬ 中宮寺跡史跡公園
- 中宮寺は、現在、法隆寺東院伽藍(夢殿)の東側にあるが、元来は東500mのこの地にあった。聖徳太子の母穴穂部間人皇后(あなほべのはしひとこうごう)の宮殿であったのを、太子が寺とし、母の菩提を弔ったと伝える。これまで数度に渡って行われた発掘調査の結果、塔、金堂が一直線に並ぶ「四天王寺式伽藍配置」であったことが明らかとなった。これは天智天皇9年(670)に火災で焼失する前の、聖徳太子が建立した斑鳩寺(法隆寺若草伽藍)と同じ伽藍配置。中宮寺跡は平成2年に国指定の史跡となり、平成30年に中宮寺跡史跡公園としてオープンした。10月には一面に秋桜が咲き誇り、見ごろを迎える。
-
- ⑭ 駒塚古墳
- 全長およそ49mの前方後円墳。古墳の名称は聖徳太子の愛馬「甲斐の黒駒」を葬ったとの伝承に由来する。「甲斐の黒駒」は甲斐国(現在の山梨県)から聖徳太子に献上されたと伝える名馬で、太子はこの「甲斐の黒駒」にまたがり、3日間で、甲斐・信濃(長野県)・越(北陸地方)を巡ったと伝承される。平成12年度から14年度にかけて行われた斑鳩町教育委員会による発掘調査の結果、古墳時代前期(4世紀後半)の築造であることが明らかとなった。幕末には、国学者で、天誅組の参謀を務めた伴林光平がここに住んだ。斑鳩町指定の史跡。
-
- ⑮ 調子丸古墳
- 駒塚古墳の南方約100mのところに位置する古墳で、『大和名所図会』にも「調子丸塚」として描かれている。古墳の名称は、聖徳太子の愛馬である「甲斐の黒駒」の馬丁(世話係)であった調子丸の墓という伝承に由来する。調子丸(調子麿)とは百済の聖明王の甥で、来日して聖徳太子に仕え、84歳で亡くなったと伝わる。現状では直径約14mの円墳だが、周辺で行われた発掘調査の結果、5世紀頃に造営された直径30m級の円墳と考えられている。斑鳩町指定の史跡。
-
- ⑯ 上宮(かみや)遺跡公園
- 奈良時代の大規模な建物群跡で、平成3年度の発掘調査で見つかった。平城宮や平城京で用いられた瓦と同じ文様の瓦が見つかっていることから、称徳天皇が行幸の際に宿泊した「飽波宮」の跡と考えられている。聖徳太子が最愛の妻・勝菩岐美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)とともに晩年を過ごした「飽波葦垣宮(あくなみあしがきのみや)」も、この付近にあったとされる。この辺りの字名を「上宮(かみや)」というが、聖徳太子一族の上宮王家(じょうぐうおうけ)にちなむとされる。
-
- ⑰ 成福(じょうふく)寺跡
- 聖徳太子が晩年、勝菩岐美郎女とともに住んだといわれる「飽波葦垣宮」の跡地に、嘉祥2年(849)に僧実乗が創建したと伝えるが、現在は廃寺となり、周囲を金網フェンスで囲まれ、自由に中へ入ることはできない。前を通る道は「太子道」で、フェンス内に「太子道」の石碑が見える。聖徳太子が薨去(こうきょ)した地について、『日本書紀』では斑鳩宮(法隆寺の東院伽藍周辺)、「大安寺伽藍縁起幷流記資材帳」には「飽波葦垣宮」、『太子伝略補注』や『古今目録抄』などでは「葦垣宮」と記されている。
-
- ⑱ 飽波(あくなみ)神社
- 聖徳太子が創建したと伝わる神社で、素盞嗚尊(すさのおのみこと)を祭神とする。東安堵・西安堵の総鎮守社。聖徳太子が晩年を過ごし、亡くなったとされる「飽波葦垣宮」の伝承地の一つ。神社の前を通る道が「筋違道」とも呼ばれる「太子道」で、聖徳太子は愛馬の「甲斐の黒駒」にまたがり、居住していた斑鳩宮と飛鳥とを往復したと伝えられる。境内には聖徳太子が腰を掛けたという「腰掛石」がある。神社の「本殿」と同社に伝えられている「ナモデ踊り道具」は奈良県の指定文化財になっている。
-
-
アプリでコースを検索する(アプリDL画面へ)
-

-